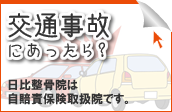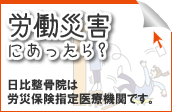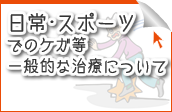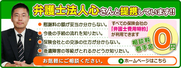- ホーム
- 体のためのお役立ち知識
- 一般雑学
- ロコモティブシンドロームのチェック
ロコモティブシンドロームのチェック
以前のお役立ち情報にもロコモについて書きましたが、今日はその続きになります。
ロコモティブシンドローム(略称:ロコモ、和名:運動器症候群)とは、「運動器」の機能に障害が起きて、立つ・歩くといった「移動機能」が低下した状態のことをいいます。
運動器とは、骨や関節、軟骨、筋肉、神経などの総称です。すべての運動器は単独で機能しているのではなく、連携して働くことで体を動かすことができる仕組みになっています。
運動器とは、骨や関節、軟骨、筋肉、神経などの総称です。すべての運動器は単独で機能しているのではなく、連携して働くことで体を動かすことができる仕組みになっています。
ところが、運動器のうちどれかひとつでも故障したり連携がとれなかったりすると、その影響は体全体に及んで体を動かすことに支障が出ます。そのためロコモが進行すると、
要介護や寝たきりを招く恐れがあるのです。
40歳以上を対象とした調査によると、ロコモは予備群を含め約4,700万人と推計されています。
40歳以上を対象とした調査によると、ロコモは予備群を含め約4,700万人と推計されています。
以下の7項目のうち、ひとつでも当てはまればロコモティブシンドロームが疑われます。
1. 片足立ちで靴下がはけない
2. 家の中でつまづいたり滑ったりする
3. 階段を上がるのに手すりが必要である
4. 横断歩道を青信号で渡りきれない
5. 15分くらい続けて歩けない
6. 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である
7. 家の中のやや重い仕事(掃除機の使用、布団の上げ下ろし等)が困難である
ロコモティブシンドロームを予防するには、
ロコモを防ぐには、運動によって骨や筋肉に適度な刺激を与えることが大切です。筋肉は高齢になってもつけることができます。
特に足と腰のまわりの筋肉を鍛え、丈夫な足腰を維持することがカギとなります。
スクワットや腹筋など軽い運動でよいので、毎日続けられる運動を心がけましょう。